1.
―――――予感はあった。試験前のあの日、ミスドで妙にそわそわしてたし、つくしと草野くんのこと、すごく羨ましそうな視線でじっと見てたし。『送る』と言って譲らなかった帰りも、ひたすら『あの2人、いいね』というような内容を幾度となく繰り返していた。あの単細胞バカの考えることなんてお見通し。2人きりで出かけるのが羨ましくて仕方ないに違いない。でも、正面切って『2人で遊びに行こう』と誘えない辺りが、あいつの可愛いところであり、鬱陶しいところでもあるのだけれど―――――
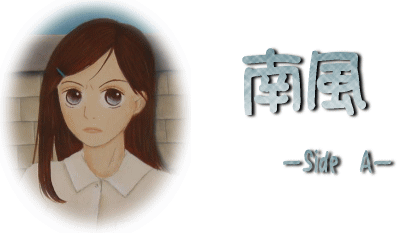
「あれ?珍しいじゃない。あんたがこんなに早く起きてるなんて、しかも鏡の前に立ってるなんて」
日曜日、午前8時。休日なんていったら、昼近くまで惰眠を貪り、2時頃ようやく勉強を始めるというのが、最近の主な行動パターンだったのだけれど。しかも今日は試験明けの日曜日ということもあって、普通なら1日中ベッドの上でごろごろ転がっていたいところだけど。
「んー・・・ちょっとね」
物珍しそうに、ヒトの後ろから鏡を覗き込むヒロコさん――あたしの母である。もちろん、産みの――に、あいまいに答える。彼女は朝8時という早い時間にも関わらず、完璧にメイクをして、完璧に髪もセットして、ベージュのパンツスーツに身を包んでいた。
「出かけるの?」
「ちょっとゲストスピーチ頼まれちゃいまして・・・」
「嘘つき」
「はい、嘘です」
彼女は悪びれもなく笑ってそう言うと、香水のビンを2.3回プッシュし、バッグ――彼女お気に入りのBALLYのもの。本皮製で、これを買うのに彼女はかなりの散財を強いられたはずだ――を肩にかけ、言ってきますと言う。
「ちょっと、ホントはどこ行くの?」
「講演会の手伝いー」
既に玄関先に消えた彼女。遠くからかろうじて声が聞こえる。彼女は福岡大学の事務職員をしている。そのつながりで、教授の講演会やシンポジウム、同窓会なんかが開催される時にはいつも借り出される。もちろん報酬はゼロだけれど、終わった後の打ち上げや2次会3次会で、普通では口に入れられないモノをゴチソウになれるからやめられない・・・そうで。ある意味、はた迷惑である。めちゃくちゃに酔っ払って帰ってくる彼女は、おそらく今日も午前様で、机に向かって必死に『受験勉強』する娘に向かって『エロ教授がむかつく』とか『お前だけが仕事で辛い目に遭ってんじゃねーよバカ課長』とか、思い切り管を巻くだろう。でもまあ、そんな仕事と人付き合いが大好きで、明るい性格の彼女のおかげで、『父親』のいない我が家――父親は3年前、夜釣りをしていて足を滑らせ、情けないことに堤防から落ちて溺死した――は、質素ながらも幸せな生活を送ることができるのだけれど。
「帰りは遅いの?」
返事は明白だけれど、一応聞いてみる。あたしと彼女の間の、社交辞令みたいな言葉。
「もちろん。おいしいお酒とおいしい肴をいっぱいおなかに入れて、最高の気分になってから帰って来る」
「気をつけてねー」
半ば呆れて、玄関に向かって声を飛ばす。
「はーい・・・ってあら、おはよう。朝早いのにどうしたの?」
ドアを開ける音が小さく響き、そのまま出かけるのだと思いきや・・・その足取りはぴたりと止まったようで。どうしたのかと思い、耳を澄ませばヒロコさんの半オクターブ上がった声が耳に届く。歯ブラシ片手に、コップに水を注いでいたあたしは、その一言で一気に嫌な予感が高まって。その反面、やっぱり来たか・・・という確信が強まって、とりあえず歯ブラシ投げて玄関へ走った。
『誰が来たの』なんてアタリマエの文句なんて言わない。ヒロコさんと向き合ってるのは、もちろんあたしが来るであろうと想像していた人物だ。相変わらず奇抜なカッコして、髪の毛立ててピアスして、『ヒロコさん、めっちゃ素敵なカッコしてますね。さすがユカちゃんのオカアサマだー』などと歯の浮くようなお世辞をさらりと言ってのける人物なんて、こいつ以外に知らないけれど。
「もう、テツヤくんったら朝から上手なんだからぁ!」
おばさんよろしく、ヒロコさんは手を口に当てて、彼の肩を軽く叩く。叩かれる方もまんざらじゃなさそうに、だらけた笑顔浮かべちゃって。『俺、ホントの事しか言わないんですよ?』だってさ。わかってはいたことだけれど、あたしは呆れずにはいられない。ふぅ・・・と大きく溜息ひとつ。そうしたら、ぴくり・・・と片耳が動くのが見えて。来る・・・と思った瞬間、家の中に目を向けて、それはもう、見ているほうが驚くぐらいに破顔して笑った。

「おはようユカちゃん!」
寝起き姿――普段から巷でよくいう『パジャマ』というものを着用しないあたしは、長袖のTシャツにハーフパンツといういでたちだ――も可愛いね・・・という、相変わらず歯の浮くようなお世辞を遮って、あたしは彼を睨みつける。
「お前帰れ、今すぐ帰れ、とっとと帰れ」
容赦なく言葉を叩き付けて、玄関の外を指差す。結構な迫力だと思うのだけれど如何せん、どうしてこのオトコには伝わらないのだろうか、全く。あたしの言葉など全くもってさらりと交わし、その上、ヒロコさんまでもがこいつの味方につくものだから。
「ユカ!女の子がそんなこと言っちゃダメ!男の子にはあくまで優しく。それにテツヤくんくらいよ、そんながさつなあんたのこと、こんなに好きって言ってくれるのは」
「うん、俺ユカちゃん大好きだから」
こらそこの2人!あたしの存在無視するな。っつーかヒロコ、お前はとっとと仕事に行けよ。しかもあたしはがさつじゃない。ちゃんと家事もこなすし、ザル勘定のあんたの財布の紐、きゅっと縛って毎月やりくりしてるのは、一体誰のおかげだと思ってるわけ?・・・というような内容の言葉を怒鳴りつけてやりたかったけれど、大きく深呼吸して、何とか思いとどまった。
「・・・ヒロコさん、時間」
何とか笑顔を作ってそういうと、彼女は腕時計で時間を確認する。やだもう、こんな時間・・・なんていいながら、急いで走り出すものだから。
「階段、気をつけてね」
以前に一度、全く同じシチュエーションで、彼女はコーポの階段を、それはもう勢い良く滑り落ちたことがある。その日は買ったばかりのチャコールグレーのスカートスーツを着ていて。ストッキングはもちろん、スーツの上下とも擦れたり汚れたり穴が開いたりする始末。もちろん自業自得だから、彼女は誰を責めるわけにも行かなかったけれど。二の舞はさすがに踏んでほしくない。だから、一応忠告。
「わかってる、そんなドジはしないわよ!」
どうだか・・・と突っ込みたくなったけれど、まあ、そこは許してあげよう。サンダルつっかけて外に出て、無事に1階までたどり着いたヒロコさんに、いってらっしゃい・・・と手を振る。ついでに、あたしの隣ににへらと並んだこいつまで。
ヒロコさんはくるりと振り返り、にやり・・・と笑った。良からぬ悪戯を思いついたときの、いつもの表情。なにか来る・・・と思った瞬間。
「ユカー、テツヤくんと自分の体は大切にしなきゃダメよー。お嫁に行くまで清い体でいなさい・・・なんて古臭いことは言わないけど、『できちゃった結婚』には反対だからねー。死んだパパにも申し訳立たないし」
んなっ・・・・バカか、あの人は・・・
「そんなことあり得るわけないっつーのっ!!」
「心配しないでください!そんなへま、俺絶対しないから!!」
そんな相反する2つの言葉が響いたのは、ほぼ同時だった。
2.
「はいどーぞ!」
ダイニングテーブルに、水の入ったコップを乱暴に置く。ピチャ・・・と小さな音がして、数滴、水がこぼれた。
「ありがとう」
幸せそうににへらぁぁぁ・・・と笑うこのオトコの顔を見て、さらに苛々が募る。こんなオトコ、水道水で十分だ!塩素とダイオキシンまみれになって死ね!・・・と思ったけれど、それはさすがに可哀想から。(それ以前に、大げさだから。)冷蔵庫からミネラルウォーター出してあげた。あたしって優しいと思う。全く。

「で、ご用件は?」
2人暮らしにふさわしい、小さなダイニングテーブル。必然的にこいつの正面にしか座れなくて。小さなため息ついて椅子を引く。その間も、ずっとあたしの顔を見てニコニコしちゃって。・・・なんか、毒気抜かれた。
「今日、マサムネとつくしちゃん2人でお出かけするんだよねー」
「お出かけじゃなくて、野球観戦」
ここはきちんと訂正。次のセリフは完全に予想できるから。奴の喉が動いて、口を開けた瞬間、あたしも同じ動作をする。
「俺たちもお出かけしよう」
「俺たちはお出かけしまぜん」
2人の声が、同時に響く。でも、語尾は180度逆の意味。一瞬だけ驚いた表情で目を丸くして、そしてまた笑った。
「俺たち、気が合うね」
「いや、合わない。言ってる言葉、全く逆の意味だから」
「どこ行く?俺、ユカちゃんが行きたいところならどこでもいいよ?」
「だから行かないって・・・」
「女の子が着替える部屋に、いちゃいけないよね。それは常識知らずの非常識ってものです。いいよユカちゃん、ゆっくり準備してよ」
「いやだから・・・」
「俺、外で待ってるから。準備できたら声かけてね」
「あの・・・」
行かないと声をかけるまもなく、あたしに向かってひらひらと手を振ると、飲み終わったグラスをシンクに置き、玄関へと向かう。
「ちょっと、あたしまだ出かけるなんて言ってない・・・」
「女の子は支度に時間かけていいからね、俺、どれだけでも待ってるから」
靴を履きながらやっぱりにへらぁぁ・・・と笑って、あたしを振り返る。その笑顔には、『断られる』とか『一緒に出かけられない』とか、そんな不安は微塵もないみたいで。・・・こんなの見せられたら、降参するしかないじゃん。幸福の絶頂にいる人間を奈落の底まで突き落とせるような度胸、あたしは持ち合わせていないし、それ以前にそれほどの仕打ちをこいつにしようと思う程、あたしはこのオトコが嫌いじゃない。
小さな諦めの溜息をついたら、自然に顔がほころんでしまう。あたしもダメだな。まだまだ甘い。昼間やろうと思っていた古典の問題集は、寝る時間を少し遅くすればそれで問題ない。明日多少眠くたって何とかなるだろう。
「・・・あんたが着替えを覗くとか、襲い掛かってくるとかそんなこと思ってないから、部屋で待ってればいいじゃない。聞きたいCDあれば出すから、それ聞いてて」
手招きをして、彼を共有ルーム――3DKから成り立つ我が家は、1部屋をヒロコさん、1部屋をあたし、1部屋をリビング兼OAルームとして使っている――へ入れる。音楽好きの父が買った――というか、遺した――KENWOODのオーディオをオンにすると、最近ブックオフで買ったDef Techのアルバムが流れだした。
「ユカちゃん、これ買ったんだ?俺持ってたのに・・・」
「買う前に言えよ」
「いや、興味ないかなと思って・・・ちょっとラップ入ってるし」
「文句は聞きません!」
ソファにおいてあるクッションを掴み、奴の顔に思い切りぶつける。
「着替えてくるけど、お前覗くなよ!覗いたら蹴る!」
もうひとつクッション持って投げつけると、奴はひょい・・・とそれを避け、『待ってるね』と、いつものだらしない笑顔で言った。
南風 ―Side B― へ
BGM♪南風レミオロメン