みぞれ混じりの寒い夜だった。
夕方からポツポツと降り始めた雨は、瞬く間に雨足を強め、
季節外れの台風を思わせる激しさで窓を叩いている。
気温があと1℃低かったなら、街の貴重な雪景色でも楽しもうと、
彼女を連れ出すこともできたかもしれないが・・・。
こうも冷たい雨では、ただ忌々しいばかりである。
司は結露に濡れた窓を見やりながら、細々と噴出すファンヒーターの
温風に手をかざした。
なにしろこの部屋は寒い。
最新の空調設備を整えた大邸宅生まれの彼には耐えがたい寒さ。
時折、どこからともなく入り込む隙間風が、さらに彼の体温を奪っていく。
この家の住人である彼女が、同じ部屋にいるにも関わらず、彼から数メートルも
離れた場所で、彼の存在を無視し続けていることも寒さの理由の一つだった。
「おい、牧野・・・」

できるだけ何気ない素振りで近づいてみる。
姑息な手段だとは思うが、肩を抱くぐらいいいだろう?
けれど、つくしは素っ気無く彼の期待を裏切り、
「んー・・・もう少し・・・」
と、一時間前と同じセリフを繰り返す。
今、彼女が全神経を向かわせているものは、ちゃぶ台の上に広げられたノートと
数冊の参考書である。その視界には司の髪の毛一本すらも入っていない。
彼女の目はひたすらにノートを走る鉛筆の後を追って左右に動いている。
彼の存在など思考の片隅にもないような様子に加えて、それを申し訳ないと
頭を下げる気配もないから、司の眉間の皺は深まるばかりであった。
まったくバカにしている。
だいたい家を訪れた時も彼女は、「どうしたの?」と少しばかり迷惑そうな
顔をした気がする・・・。
「あのね、あたしには約束された将来なんかないの。なんだかんだ言って結構
さぼっちゃってるし。進学するなら今からやっとかないとすごーくマズイの。
わかる?」
「んなの、俺が理事長にうまく言っとけば一発だろ?」
「やめてよ、みっともない。それに我が家に英徳に上がるお金あるわけないでしょ。
あたしが目指してるのは国立一本。自力で頑張らなきゃ」
テスト直前のため、目下、猛勉強中のつくし。
「キリがいいところで終わらせるから」と言って、薄っぺらい座布団を差し出し、
目線はもう卓上の参考書へ。
こうして、ページを捲る音に耳を傾けること一時間。
かなり高い確率で現実になりそうな想像が、司を忍耐の限界に立たせていた。
いくらなんでもまさか・・・一応、コイツも女なんだし・・・。
いやでも・・・この女なら充分ありえる・・・・。
「・・・お前・・・・今日が何の日か覚えてるか?」
「なに?いきなり・・・」
「2月14日」
人差し指を顎にあてて小首を傾げる彼女を見れば、答えを待つまでもない。
「・・・あっ!」
案の定、つくしは咄嗟に顔を顰めて立ち上がった。
「急いで買ってくる!」
信じらんねー・・・用意もしてねぇのかよっ!
「───正直に言うと、彼は今朝からずっと彼女を待っていた。
せめて今日という日ぐらいは女から電話するのが当然で、
男から連絡を入れるのは、なんだかひどく格好悪いから。
本当はすぐに逢いたいのに、ぐずぐずと時間ばかりが過ぎて。
黒い雲で覆われていた空から、ついに雨が落ち始めたのをきっかけに、
もう待ちきれないと急いで自宅を飛び出したという情けない経緯。
「ふざけんな、もういい」
司はあからさまな不機嫌顔で背中を向けた。
つくしは初めて申し訳なさそうに手を合わせ、彼を覗き込むように腰を折る。
「ごめん、そんなに怒らないでよ」
「・・・・・・」
「・・・それとも道明寺も一緒に選ぶ?」
外は横なぐりの冷たい雨が降っている。
出歩けばそれはきっと、たちまちに彼女を濡らし凍えさせてしまうだろう。
「・・・・。じゃあ行ってくるね」
壁に掛けたコートを羽織り、奥の引き出しから財布を取り出すつくし。
納得いかない苛立ちと、ふと胸に満ちる罪悪感・・・。
司はふて腐れたまま、つくしの腕を取り引き寄せる。
彼女の短い悲鳴を無視して、絡ませた両手の指を畳に押し付け、
倒れた勢いで跳ねた膝を開き、強引に片足を割りいれる。
「あ、あのぉ・・チョコは・・・?」
驚きのあまり、つくしは少し怯えた視線を上げる。
「いらね、別のもん貰う」
司はようやく表情を緩め、一瞬過ぎったその恐怖を取り除くべく、
つくしの耳元に囁いた。
結局のところ、彼は彼女を独占したいのだ。
学校も仕事も未来も含めた、彼女の全部が欲しい。
それこそ生活の隅々まで、なにもかもを。
我ながら呆れた独占欲だと、司も思う。
もちろん、将来に夢を馳せて困難に立ち向かう彼女の自由な逞しさは、
牧野つくしという女に欠かせない魅力であることもわかっている。
だからこそ彼は、そのいきすぎた主張を泥を飲むような息苦しさで耐えてきたのだ。
・・・・でも、今日ぐらいは。
彼女を自分に縫い付け、ただすべてを縛ってしまいたい。
重ねた体の下で彼女もまた、赤く染め上げた首筋で彼を甘く拘束する。
熱い血流はつま先まで駆け巡ってゆくのに、心は凪いでいるその不思議を感じながら、
雨音が満ちる冷たい夜、司は彼女の唇を奪った。
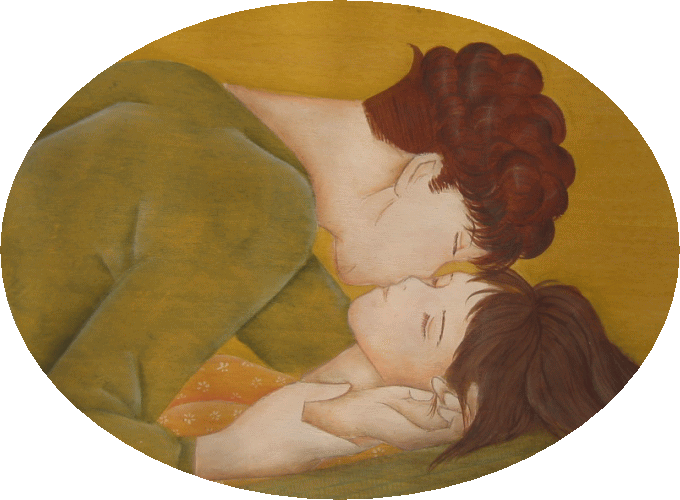
fin
急いで書いてUPしたのでかなり雑な仕上がりになってしまいました。スミマセン sweetberry
