
正月三日目、年賀の客に紛れて、家を抜け出した・・・。
「・・・同じ洋館って言っても、ウチとはずいぶん違うな・・・。」
あきらは、三条邸を見上げていた。
表通りから少し奥に入った所に、まるで時代から忘れ去られたようにそれは建っていた。
「明治半ばか、新しくても大正年間ってところだろう・・・。」
蔦の絡まる石造りの壁や、苔生した石畳、きれいに刈りこまれている年代物の植木を見てつぶやく。
「これはこれで、なかなか風情があるもんだな・・。」
玄関に立って声をかけてみると、しばらくしてから返事があって,桜子本人が出てきた。
「・・すみませんお待たせしちゃって・・,お正月なので通いのメイドたちはお休みなんです。」
ちょっと困ったように首をかしげて言うのに、あきらは慌てて答えた。
「・・いや、別に・・静かでいいな・・ここ。」
取引先の社長だの・・関連会社の重役たちだの・・
年賀の客で賑わう我が家を思い浮かべて言う。
「美作さんって、お上手ですね・・ま、さびれてるって言われても私は平気ですけれど・・。」
少し眉を顰めて笑う桜子に、慌ててあきらは首を振った。
「いや、まじで・・。」
おもむろに、表情を改めて言う。
「明けましておめでとう、今年も・・何かとよろしく・・な。」
答えて、桜子も深々と頭を優雅なしぐさで下げた。
「おめでとうございます、こちらこそ、よろしくお願いしますね。」
顔をあげて、どちらからともなく微笑かわす。
「なんだか、変な感じですね・・。」
「いいんじゃない・・一応けじめだし・・。」
「そうゆうところ、美作さんって真面目ですね・・。」
「そうかな・・そんなことより、それ・・いいわ・・。」
桜子の装いに話題を転換する。
古代紫の地に純白の牡丹の柄、
白銀の花びらに金糸の花芯の縫い取りがある少し古風な大振袖に、
金銀吉祥紋の袋帯の組み合わせである。
普段よりも色合いの濃い髪はゆったりと結い上げられて、
見事な深紅の珊瑚の簪がただ一つの飾り、
同じ色の伊達衿と映えている。
閑散としていた玄関ホールに桜子が立つと、そこだけ花が咲いたように明るい。
まるで、中原淳一か竹久夢二の美人画から抜け出したようなしっとりとした立ち姿に、
あきらは思わず感嘆の声を挙げていた。
「こんな美人を連れて歩けるなんて、光栄だよ・・・。」
思わず賞賛してしまってから、相手があの桜子だったことに気が付いて苦笑する。
桜子も、似たような気分だったのかも知れない。
「いつもいつも、そんな風に誰かさんに調子のいいこと言っているのでしょう・・・。」
少しばかり鼻白んだ顔をしたが、すぐににっこりと笑って答えた。
「でも、女にはうるさい美作さんに、誉めてもらえるのは悪くないかもしれませんね。」
「・・・・・。」
言葉をなくしているあきらの顔をのぞきこんで、桜子はくすりと妖艶に笑う。
「・・母の形見なんですよ、これ。」
「・・・・・。」
「・・とりあえず・・初詣ですか・・平凡だけど・・。」
車に乗りこんであきらが言うと、桜子も答える。
「・・そうですね、今年はいい年になりますように・・。」
「桜子みたいな悪女でも、そう思うんだ・・?」
まぜっかえすと、少し膨れた風に答える。
「去年は誰かさんたちに、振りまわされた一年でしたからね・・
今年こそは自分自身の幸福をお願いしたいです。」
「そりゃ、まったくもって同感・・。」
「・・でしょ?」
心の真底から同意する。
「あいつらの幸福も祈ってやっておこう、
・・ でないと、いつまでたってもこちらにまで幸運が巡ってこないような気がするぜ。」
「美作さんって、本当にいい人ですね・・。」
あきらは、苦笑した。
「お前に言われると、誉められてるような気になれねえや・・。」
「なんですか、それ・・?」
桜子は笑いながらも、軽くあきらを睨みつけた。
都心は混雑がひどいからと、あきらが向かったのは海にのぞんだ古い都だった。
「ここだって、混むので有名なのじゃなかったですか・・?」
眉を顰める桜子に笑って言う。
「人が集まるってことは、そんだけご利益があるってことかもしれないぜ・・。」
「・・・・・。」
「・・それに、ちょっといい手があるからさ・・。」
「・・・・・。」
表の参道からは、少しばかり奥に入った閑静な屋敷街の一角に車は止まった。
そこには瀟洒な作りの、いかにも由緒ありげな日本家屋があるだけである。
「・・ここは・・?」
怪訝そうな顔の桜子に、にやりと笑って言う。
「まずは、お参りに行ってこようぜ・・・。」
運転手になにか言い含めると、あきらはさっさと歩き出した。
「ま・まってください・・。」
あきらは勝手知った様子で、いくつかの路地を抜けて歩いていく。
その歩き方は速すぎず遅すぎず、着なれない和服の桜子にも、丁度よかった。
「・・ここだ・・・。」
小さな山門を入って少し坂道を登る。
歩きにくそうな所に差し掛かると、さりげなく手を貸してくれる。
マメなことだと最初は呆れていた桜子だったが、それが次第に心地よく思えてくる。
そう思えるほどに、あきらの所作はあくまで自然で厭味がなかった。
しばらく行くと、いつのまにか拝殿の間近に来ていて、参拝の長蛇の列が続いていた。
あきらは、するりとその途中へと潜りこんで桜子を手招きする。
「ほら・・はやく・・。」
「これって・・横入り・・・って言うのじゃ・・。」
ためらう桜子に、逆に尋ねる。
「じゃ、あの下から並んでみる・・?」
二人を見咎めて、何かを言いたそうにしている晴れ着姿の女の子の集団に、
にっこりと微笑みかけながら、あきらは言う。
小さな不平の声をあげていた集団は、たちまちのうちに静かになった。
桜子が指差さされた方向を見ると、石段の下、参道を延々と続いている人波が見える。
その列は遅々として、全く動いているようには見えない。
「・・いえ、・・ここが、いいです。」
今度は桜子が横目であきらを睨みつけていた前の男に、
にっこりと極上の笑みを送りながらこたえた。
その男は照れたように咳払いをすると、視線を和らげる。
「・・・だろ・・・。」
あきらは片目をつぶった。
「・・ですね・・。」
「そろそろ寒牡丹が咲いているはずなんだけど・・?」
一応の形通りの参拝を済ませたあと、庭園の方に二人は向かった。
参道の賑わいがまるで嘘のように、広い境内では人波が少なくなって静寂が広がっている。
冬のうら寂しい景色の中にも、松の緑や寒椿の鮮やかな紅などが池の水面に映る中を、
ショールの前を掻きあわせながら、桜子はあきらから半歩遅れて歩いていった。
文句なく美しい二人連れに、すれ違う人が振りかえって行く。
その視線のくすぐったさに、桜子は知らず知らずのうちに笑みを浮かべていた。
ふと、すれ違う若い男女の会話を桜子は耳に止めた。
「ベンツのリモだぜ・・・俺近くで見たの初めて・・。」
「すごかったね。」
「ただ、こんなに混雑してるところに来るのはなんだか・・だな。」
「うん、運転手さん困っていたね・・立ち往生しちゃって。」
「あの男、偉そうに怒鳴っていたし・・。」
「・・・・・。」
歩調をゆるめて桜子が聞き耳をたてていると、側に立つあきらがつぶやく。
「・・・まさかな・・。」
顔を見合わせて、お互いが同じことを考えていることに気がつく。
「・・・まさかと思いますけれど・・。」
「・・・・・。」
突然あきらの足がとまって、足元に気を取られていた桜子は驚く。
「美作さん・・?」
「しぃ・・!」
不意に手首を捕まれて、椿の木の陰に引っ張り込まれた。
「・・どうしたんですか・・・?」
「・・静かに・・。」
手振りでしゃがむように促されて、着物の裾を気にしながらも渋々従った。
首をかしげた桜子の耳に、聞いた覚えのある声が入ってくる。
「・・もうっ、信じられないっ・・!!」
「・・なんだよ・・。」
「まったく・・・どこに、ひいたおみくじが気に入らないからって、替えてくれなんて言う人がいるの・・?」
「・・だって、仕方ねぇじゃん。」
「それで断られたら、今度はここにあるおみくじ全部買い占めるって・・?」
「イイだろ、金はあるんだし・・タダでって言ってるんじゃないし。」
「馬鹿言ってるんじゃないって、そんなことしたら他の人が迷惑するでしょっ!!」
「そんなこと知るかよ・・。」
バコ・・!
司の頭につくしのパンチが炸裂する。
あきらの肩がびくっと揺れて、殴られた本人よりもはるかに痛そうに顔をしかめたのが、桜子にはわかった。
「いってぇな・・・なにすんだよ・・この暴力女!」
「あんたって、いつまでたっても進歩がないヤツね。」
「うるさいんだよ!」
「さっきは渋滞してるのが気に入らないからって、警視総監に電話するって言ってたし・・。」
「終わったことを、いちいち蒸し返すんじゃねぇ・・やってないから、いいだろがっ!」
「参道が混雑してるのにも、文句ばっかり言ってたじゃない・・!」
「あんなに、ゴチャゴチャしてるのに慣れていないんだよっ!!」
「・・本当に・・もう・・!!」
「・・やれやれ・・・。」
あきらがため息をつくのが聞こえた。
桜子はくすりと小さく笑う。
「・・こんなところで出会うとは思いませんでしたね。」
「・・ああ・・今年も、あいつらに振り回される一年かも・・な。」
「・・・・・。」
「・・一年の計は元旦にあり・・っていうだろ。」
「・・でも、今日は3日ですよ。」
「・・そうだけど・・さ。」
気弱に微笑むあきらを励まして言う。
「・・雨降って地かたまる・・とも言いますから・・。」
「そう、願いたいけれど・・。」
いつまでもそっぽを向いている二人に、あきらがイライラしているのがわかる。
「・・やっぱ・・俺たちが出ていってやらないと・・。」
腰を上げそうになるあきらの肩をおさえて、桜子は言う。
「もう少し・・待ってみましょう・・。」
「しかし・・。」
「甘やかしちゃダメですよ。」
「・・・だけど・・・。」
「・・いいから・・・。」
「・・・・・。」
しばらくすると、ふくれているつくしをなだめるように、司が切り出す。
「なあ、牧野・・。」
「なに・・?」
素直に返事をしたところを見ると、そんなに怒っていたわけでもないらしい。
「お前さ・・一年の初めに引いたおみくじが、大凶で何とも思わないのかよ・・。」
「そりゃ・・気にならないことはないけれど・・。」
下を向きながら、つくしが答えているのが見える。
「これはこうして、結んでおけばいいし・・。」
木の枝におみくじを結びつけながら答える。
「この一年、注意しなさいって・・ことなんだよ、きっと。」
「・・・・・。」
「そのせいで悪いことを、少しでも避けられたらいいじゃない。」
「あらあら・・先輩ったら大凶ひいちゃったんですね・・・大変だわ。」
桜子はつぶやいた。
「・・・他の神社にでも、験直しに行ってみるか・・?」
司が言う声が聞こえる。
「・・いいよ、・・・これで・・。」
「本当に・・?」
「うん、あっちにもこっちにもなんて、節操ないよ、それこそ神様に見捨てられちゃう。」
明るく笑おうとしているつくしに、司が重ねて言う。
「・・き・気にするなよ・・。」
「あれ?道明寺・・気にしているの?」
つくしが下から司の顔を覗きこむ。
「こわいものなんてない天下の道明寺サマが、おみくじなんかでクヨクヨと・・。」
からかうような口調に、司が反発する。
「ば・ばか言うんじゃねえ・・俺はおまえを・・・。」
「・・あたしを・・?」
「・・おまえのことを心配しているんだよっ!!」
「・・・・・。」
つくしは真っ赤な顔で、口をパクパクさせるばかり。
「・・何があっても、俺が守ってやっから・・・いいな。」
「・・・・・。」
「わ・わ・わかったな・・・。」
言った本人も、照れくさいのか赤面してあさっての方を見ている。
「・・くくっく・・・。」
口を押さえたあきらの肩が揺れる。
「ここまでの道のりの長かった事を思うと、涙がでてくるぜ・・。」
その肩を軽くたたいて、桜子は立ちあがる。
「行きましょう・・私達の出番はなさそうです・・。」
「・・だな、お兄さんは・・うれしいよ。」
嬉し涙にむせぶあきらに、桜子は暖かく笑いかけた。
「あ・あんた、・・・そ・そんな恥かしいことを・・・よく。」
「・・いいだろ・・・本当のことなんだから。」
仲直りできたことは、遠目からでも確認できた。
あきらを振りかえって、桜子がくすくすと笑う。
「なんだか安心したら、お腹すいてきちゃいました・・。」
「・・本当だな・・。」
「美作さん、なにか美味しいもの食べさせてくれませんか・・?」
「・・おう・・まかせておけ。」
あきらは胸を叩いた。
「・・あいつらの前途を祝福して・・乾杯!!」
「・・私達それぞれの幸福を願って・・乾杯!!」
「・・それぞれ・・なのか?」
「・・え?」
桜子は首を可愛らしく傾げると、複雑な微笑みを浮かべた。
「美作さん、さっきの懐石料理のお店、半年ほど前から予約しておかないと、ダメなお店ですよね。」
「・・ああ、しかも正月は特別で10ヶ月前だ・・・って、そんなこと・・・。」
驚くあきらの横顔をのぞきこんで、桜子は苦笑した。
「・・いったい、誰と行くつもりで、予約していたのでしょうね・・・」
「・・いや・・それは・・・・。」
「・・それは・・?」
にっこりと、とろけるような笑顔で問いかけられて、あきらはますます混乱する。
「いや・・だから、3日の日なら家を抜け出せるって言うから、せっかく予約しておいたのに
ダンナと出かけちゃって・・。」
「・・やっぱりね・・。」
「・・・・・。」
「かなりのこだわりのあるご主人で、一度キャンセルしてしまうと次の予約が入れにくいのですって・・?」
「・・知っていたのかよ・・・。」
あきらは青ざめる。
「つまり、予約を消化する必要があったのですね。」
「・・いや、確かにその通りだけれど・・。」
「・・・・・。」
桜子の問い詰めるような視線に、目を伏せながらも言葉を続ける。
「・・桜子と二人で出かけたいと、俺は思ったから・・。」
「・・・・・。」
「今日は純粋に楽しかったし、桜子と来てよかったと思ってるのは事実・・・。」
「・・・・・。」
「・・信じてくれなくても仕方ないけれど・・。」
「・・・・・。」
気まずく黙り込んでしまったあきらに、くすりと笑いかけて桜子は頭を下げた。
「私も楽しかったですよ、ありがとうございました。」
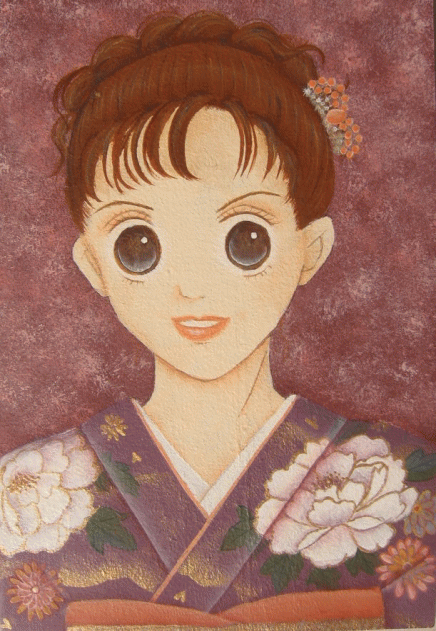
いつもの・・・おまけ
「ずっと前に聞いたことあるのだけれど、
大凶って千本に一本もないくらい珍しいのだって・・だから。」
「・・だから・・?」
「だから、これに当たるって事は、凄くついてるって・・却っておめでたことなのだって。」
「ふーん。」
「・・本当だよ・・本当の話。」
「つまり・・レア物ってことか。」
「うん、・・そう。」
「・・じゃ、あれだな・・・。」
「・・・・?」
「・・・つまり、俺様と同じってことだな・・。」
「・・・は・・?」
「めったにない、レア物・・お前は本当についてる女だ・・。」
「・・・・・。」
自分がついてる女かどうかはさておき、
コイツは確かに大凶のおみくじそのものにちがいないと思ったつくしだった。

戻る